| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 × | 9 〇 | 10 AM |
11 × | 12 × | 13 〇 | 14 〇 | 15 × | 16 〇 | 17 AM |
18 × | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 × | 23 〇 | 24 AM |
25 × | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 × | 30 〇 | 31 AM |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 × | 6 〇 | 7 AM |
8 × | 9 〇 | 10 〇 | 11 × | 12 × | 13 〇 | 14 AM |
15 × | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 × | 20 〇 | 21 AM |
22 × | 23 × | 24 〇 | 25 〇 | 26 × | 27 〇 | 28 AM |
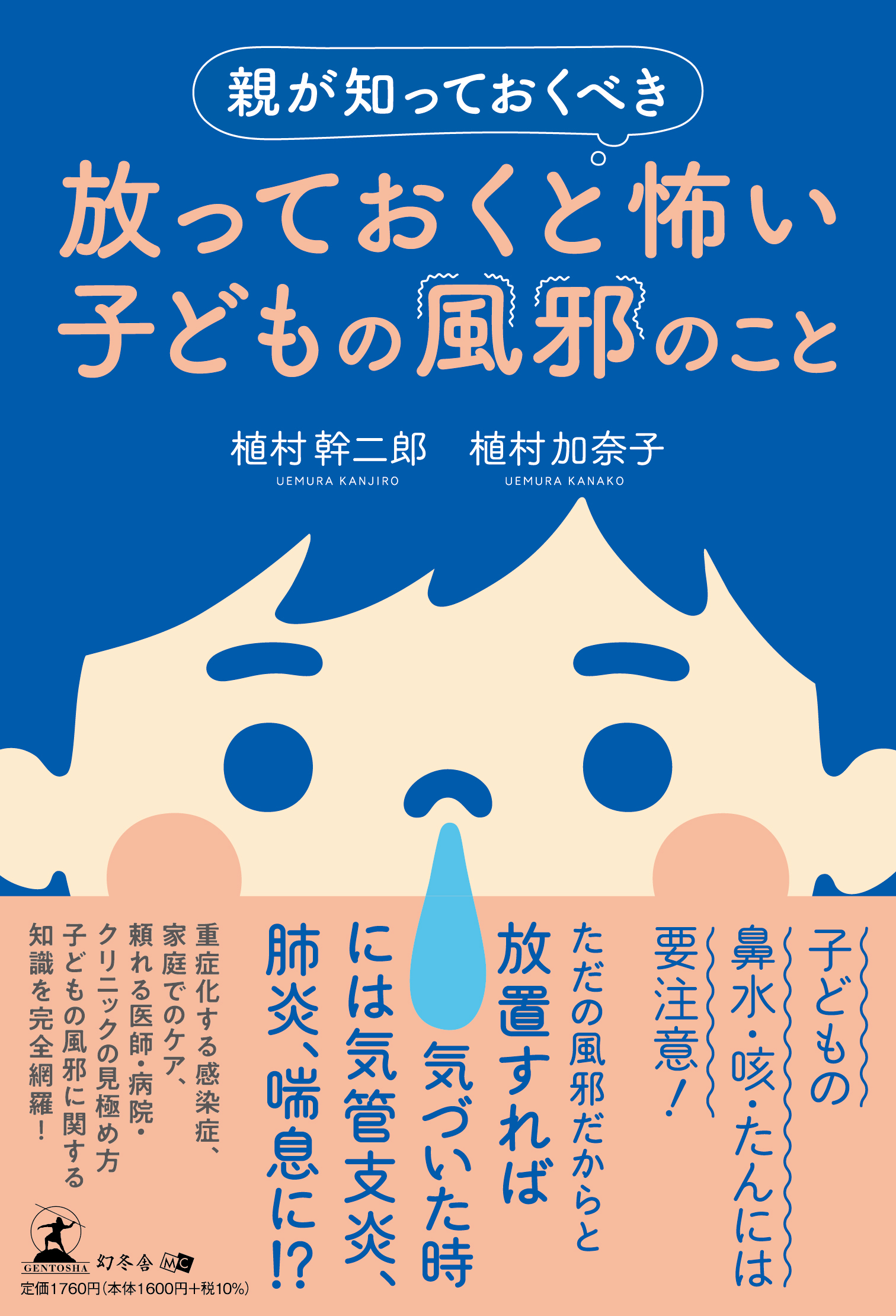
2025年10月20日に【放っておくと怖い子どもの風邪のこと】を発売致しました。院長と副院長の共著です。日頃の鼻風邪のお悩みに関して、分かりやすく読みやすく解説しました。医療従事者にも読んで頂きたく日々の診療のtipsも盛り込みました。是非お手に取って頂けると嬉しいです!
「漢方薬の誤解」
当院では漢方薬を多用しています。誤解だらけの薬でもあるのですが、例えば「ずっと飲んで1週間ぐらいたってやっと効くもの」という誤解は割と多い様です。「風邪に葛根湯を処方しますが、風邪薬が1週間後に効くって変ですね」と説明しています。芍薬甘草湯の様に服用して数分で効く漢方もあります。「子どもは苦くて飲めない」というのも誤解の一つです。漢方薬にも種類が色々あって、小建中湯・桔梗湯・麦門冬湯・甘麦大棗湯のような飲みやすい漢方もあります。乳児は味覚が発達していないので比較的スムーズに服用してくれますが、2~5歳の幼児が問題です。飲めたらしっかり褒めてあげてください。6歳以上は薬の必要性を理解してくれれば服用することが多いようです。
「ヒトメタニューモウイルス感染症の特徴」
こどもがヒトメタニューモウイルス(hMPV)感染症になり、親が遅れて風邪症状が出た複数の方からの話です。「凄い量の鼻汁が出る」「痰がらみの咳が出るが半端ない痰の量」「息苦しくて眠れない」「鼻が詰まって食べられない」などなど。こんな感染症なのです。鼻かみや痰出しが自分でできないこどもがかかれば可哀そうでしょう。保護者の方など周りの方々がその事実に気づいて物理的に気道分泌物を除去していくのが治療の筋かと思います。小児科医の中には「取ったってすぐ溜まるから同じや」という声も聞こえてきます。しかし目の前で窒息するかもというこどもの分泌物は直ちに除去していく必要があります。「咳が凄くて眠れなかったのです」と訴えた小学生のこどもが来院されました。hMPV感染症と診断(6歳以上は保険が通りません)をし、大量の鼻汁や痰を2回に分けて吸引した後「あーすっきりした。息が楽になった。眠れそうだ」と言って帰りました。次回来院時には咳もかなり良くなってすやすやと眠っているとのことでした。例年のhMPV感染症に比べて小学生以上や大人も多く見受けられます。皆様気を付けてください。
「ヒトメタニューモウイルス感染症」
数か月前からテレビ等で報道されていた病気がやはり流行してきました。「ワクチンも特効薬もない」「中国で流行し春節で日本に流入してくる」「怖い病気だ」と散々煽っていました。私たち小児科医は以前から日本では3~6月に流行する現実を見てきました。多いシーズンで50人ぐらい患者さんを診ていましたが、ここ数年はコロナ禍でほとんど流行していません。RSウイルス感染症とほぼ同じ症状で、異様に鼻汁・痰が溜まり、肺炎・気管支炎・副鼻腔炎・中耳炎のリスクが高いと言えます。幼児に多いのですが、小学生や大人もかかり、特に高齢者は要注意です。「かかったかな?」と思ったらせっせと鼻かみ・鼻汁吸引・排痰をしてください。小学生でも鼻かみや痰出しをしなければ窒息状態なることがあり、気を付けてください。
「おちんちんにまつわる話」
一番多い訴えは陰茎の先が赤くはれる亀頭包皮炎です。包茎であれば起こりやすいのですが、なくとも発症します。膿が認められれば当院では抗菌薬処方していますが、大抵は塗り薬で対応し数日で改善しています。包茎を心配して来院するお母さんも散見されます。乳幼児の包茎は一般に病的ではなく自然経過を見るだけで良いようです。小学生になっての包茎は治療の対象になります。毎日入浴時に包皮を少しずつ後退させ、ステロイド軟膏を塗っていくという方法があります。お母さんにとって頃合いが今ひとつ分からないことが多いようなので、お父さんにしてもらっています。無理に後退させたらそのまま包皮が戻らず亀頭を締め付け、先がうっ血状態に陥り、この状態を陥頓包茎(かんとんほうけい)と言います。元に戻らなければ救急疾患となります。「優しく」が原則です。
突発性発疹という病気は生まれて初めての発熱で始まることが多い6~12か月児の感染症です。HHV-6というウイルスが原因です。後になって見つけられたHHV-7というウイルスも同じように突発性発疹を起こしてきますが1~2歳に好発するようです。咳や鼻汁がないので、「風邪」とも言い難く、当初は医者泣かせです。いろいろ鑑別を要する疾患がありますが、最も多いのが川崎病です。同じように咳や鼻汁のない発熱で始まり、見分けが難しいのです。しかし発熱の割に「機嫌が良い」というのが頼りになりますが絶対的ではありません。見分けがつかないときには積極的に血液検査をしています。3日ほどの発熱後解熱して発疹が現れます。この時期は逆に機嫌がすこぶる悪い事が多く、お母さん泣かせです。機嫌が悪い理由は医学的には良く分かっていませんが、発疹が消える頃には治っています。
「インフルエンザの診断」
インフルエンザがかなり流行してきました。インフルエンザの診断は抗原迅速検査が陽性であれば簡単なことです。しかし単純な話ではありません。インフルエンザなのに陰性となる最も多い原因は、発熱から検査施行までが短い時(例えば熱が出て2時間後に検査を行った)です。子どもが急に高熱が出た場合、慌てて小児科に連れて行くのは当たり前の事で、お母さんを責めるわけにはいきません。迅速検査は一番鋭敏な方法を採用していますが、それでも陰性の場合はインフルエンザでないとは言い切れません。当院では色々工夫をしています。4年前から導入したのは咽頭所見です。典型的な咽頭所見が見られることが割にあり、これで診断することもあります。写真を撮ってAIで咽頭所見を判断するという一歩進んだ方法も採用しています。さらに今シーズン遺伝子検査を行っています。今のところ発熱して1時間以内に陽性と判断した例もあります。ただしこの方法は保険の縛りがあり全ての方に行うわけにはいきません。喘息・妊婦などの基礎疾患がある方はこの検査は可能です。また5歳未満で熱が出て12時間以内なら適応があります。12時間以上であればこの検査ができなくなり、今まで「待ってください」「明日受診してください」と言っていたのが真逆のことになります。
「OS-1を飲まない子ども」
ウイルス性胃腸炎は毎年冬に多く見られます。今年ははっきりしませんがやや増加傾向にある様です。頻回嘔吐や下痢の場合、摂取する水分はお茶・真水はよくありません。ポカリスウェットも好ましくありません。OS-1が理想ですが、甘くなく少し塩辛いので嫌がる子どもが見受けられます。そんな時にお勧めは「具たくさんの野菜の味噌汁」の汁です。この汁とポカリスウェットを半々で混合すればOS-1に似た組成になって更にお勧めです(味は保障できませんが…)リンゴジュースは理想から離れています。糖の濃度が高く電解質のバランスも悪いのですが半分に薄めると少しは理想に近づきます。どうしても飲まない場合は一応これで頑張ってください。
「もののらいはうつりません」
「ものもらい」とは眼瞼の縁にあるツァイス腺(毛根にある脂腺)、モル腺(汗腺)、マイボーム腺(涙の蒸発を防ぐ脂腺)に細菌感染が生じたことによる病気です。原因菌は皮膚に正常でもいるブドウ球菌です。ブドウ球菌の付いた汚い手でこすったり、汚染したコンタクトレンズで感染したりするのです。通称「ものもらい」は、あたかもうつるかのような名前ですが決してうつるものではありません。「治すためにヒトから物をもらう」という言い伝えが語源のようです。地方により「めばちこ」「めいぼ」など、いろいろ呼び名があります。京都府や滋賀県以外の関西では「めばちこ」が一般的のようです。
「赤ちゃんの耳掃除」
多少の耳垢であれば家庭で無理にとる必要はありません。綿棒や耳かきで習慣的に耳掃除している親御さんも少なくありませんが、入浴後に濡れた耳を軽くぬぐう程度が無難です。家庭で綿棒や耳かきを使って耳掃除をすることは常に危険を伴います。子どもは想定外の動きをするのでトラブルが起こりやすく注意が必要です。東京消防庁の報告では5年間に耳掃除中の外傷で280人が救急搬送され、そのうち0~4歳が97人(35%)、5~9歳が34人(12%)で、重症1例、入院必要例が10例となっています。アメリカでは年に10,000件以上の耳外傷、2,000件以上の鼓膜穿孔が報告され、学会レベルで明確に耳掃除と綿棒使用に反対しています。
「インフルエンザの流行」
先週になって急にインフルエンザの患者さんが増えてきています。すべてA型で、今のところこじらせた方はいません。発熱があって即刻受診という方が多いのですが、発熱があって24時間以内であれば迅速抗原検査の検出率は悪いようです。陰性であっても「兄弟が感染していた」「のどの診察所見が極めてインフルエンザっぽい」「血液検査で白血球が低下している」などの間接的ではあるがそれらしき証拠があれば総合的に判断して「みなし陽性」として対応することも行っています。高熱が出ればすぐ受診したくなる気持ちはよく分かります。その対策として本年度から当院ではインフルエンザの遺伝子検査を導入しました。5分から20分待っていただくのですが、早期でも非常に正確に検出されます。ただし保険上の縛りがあり、発症して12時間以内の低年齢児や心疾患・喘息などの基礎疾患がある方などにしか認められていません。全員に検査ができるわけではないのでご留意を。
「増えているゴマアレルギーの子ども」
子どものゴマアレルギーが近年世界的に増加傾向ですが、食物アレルギーの中ではまだ1%以下です。ゴマアレルギーの多くは幼児の即時型反応(食べて1時間以内に蕁麻疹などが出現するタイプ)で発症し、約30%がアナフィラキシーを起こす可能性が指摘されています。血液検査及び臨床症状で診断しているのですが、血液検査(IgERAST検査)で陽性だからと言っても必ずアレルギー症状が起こるとは限りません。ゴマの中でも粒ゴマより摺りゴマはリスクが高く、ゴマ油は低いとされています。食べ物としてのみではなく、色々な思いもかけないところで使われています。例えば漢方の消風散に含有されていますし、香水、化粧品、UVバリアクリーム、潤滑剤、殺虫剤などの製造にも使用されています。ピーナッツやナッツ類の他の種実類と同じでなかなか耐性ができないため治りにくいです。
「痛くない不安感の少ない予防接種を目指す」
以前から痛くない不安感の少ない予防接種を目指していろいろ努力してきました。例えば「ゲートコントロール理論」を応用した刺入部位の圧迫麻酔法で痛みを軽減する方法がその一つです。新型コロナワクチンの時大人の接種で、実際に多くの方に用い好評を得ています。最近さらにアップグレードして針の刺入部位を冷やしたり振動を加えたり、看護師が声掛けで不安感を取り去ることも積極的に行っています。子宮頸がんワクチンはデリケートな思春期の女性が対象なので、もし不安感があれば、かつて報告された異常事態に陥ることがあります。そのため不安感を少しでも払拭するよう時間をかけてお話をしています。

このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら